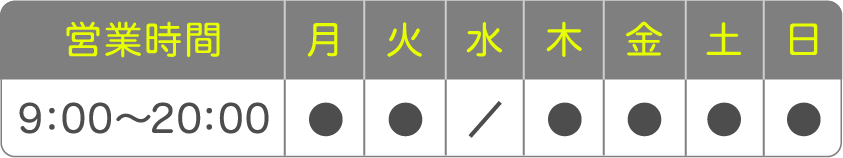当院で行っている東洋医学の経絡治療に関して解説していきます。
病院の検査で異常が見られない不調、自律神経の不調に非常に有効な治療になりますので、お悩みの方は是非ご覧ください。
経絡治療とは

経絡治療とは古代中国の理論に基づいた治療法です。
生命エネルギーの源とされる気や血が流れるルート(道)を経絡と呼び、経絡が滞りなく流れて気血が循環している状態が健康とされています。経絡は五臓六腑と連絡している為、経絡が滞ると臓腑にも影響を及ぼし、様々な不調が発生してしまいます。
経絡治療とは、鍼灸治療をすることで経絡の滞りを解消し、全身にバランスよく気血を循環させ、臓腑を健康な状態にする治療法という事です。
なぜ臓腑を健康な状態にするのか?

東洋医学には五行という概念があります。
木(肝)火(心)土(脾)金(肺)水(腎)の5つの蔵がバランスの良い状態で機能している状態が健康とされ、それらのバランスが乱れることで様々な不調に繋がるとされています。
例えば、肝は血や精神を司っているので、肝の機能が低下すると疲れ目や肩こり、不眠やイライラなど、精神症状や血に関わる不調が出てきます。その様に臓腑の状態が全身の状態を表す為、臓腑を健康な状態に保つことが重要とされています。
東洋医学の診察方法

流経絡治療では「望診・聞診・問診・切診」という4つの診察方法(四診法)を用いて経絡の気血の流れと五臓六腑の動きなど、現在の身体の状態を確認します。
望診 : 体格や姿勢、顔色などを確認します。
聞診 : 声色や声の高さなどを確認します。
問診 : 現在の病状、生活環境(食欲、睡眠、便通)などを伺います。
切診:両手足の肌の具合、腹部の硬さ、手足の冷えなどを軽く触りながら確認します。
脈診にて脈の浮き沈み、早さ、強さ、臓腑の状態を確認します。
脈を診て身体の状態を把握する脈診流経絡治療

当院で行っている経絡治療は脈診流経絡治療という治療法です。
指先で患者の脈に触れることで、脈の強弱、深さや浅さ、脈の形状を把握し、機能が弱くなっている臓を探します。脈の状態やその他の四診法で得られた情報を基に体質を決定します。東洋医学ではそれを「証(しょう)」と呼び、今の不調の原因となる体質を改善する為の治療を行います。証に応じて治療も異なる為、非常に重要な最初の診察と言えます。
証が決定した後に経絡治療では大きく2つの治療を行います。
本治法
今の不調の根本原因である五臓六腑に対する気血のバランスを肘から先、膝から下にある重要なツボを用いて調整する治療法です。気血が足りていない経絡には「補法」で補い、過剰に有り余った経絡からは「瀉法」で抜き去り、気血のバランスを調整します。
生命エネルギーの源となる精気を補う事で五臓六腑の機能を高め、全身の血流循環や免疫機能を高めていきます。西洋医学の鍼灸治療や他の治療法には無い、経絡治療独自の治療法となります。
標治法
臓腑の気血のバランスを整えた後に、実際に感じている症状に対しての治療を行います。頭痛や吐き気、内臓の不調、睡眠障害など、いま感じている症状に応じた効果的なツボや経絡に対して鍼灸を施すことで経絡の滞りが解消され症状を緩和させていきます。本治法と合わせて行う事で治療の効果が高まるので、本治法と標治法をセットで行う事が重要です。
経絡治療は効かない?経絡治療の効果

経絡治療は驚くほどやさしい刺激で行います。鍼が刺さっているか分からない程の刺激な為、効いていない感じや、やられた感じがしないという感想を持つ方もいます。リラックス効果が高く、全身の血管が緩みポカポカと身体が温まる感覚が出てくるのが特徴です。
刺激が強ければ効果が高いかと言われるとそうではありません。鍼を刺す深さは1ミリ~5ミリ程度しか刺しませんが、鍼灸治療において神経に作用させるにはその深さが一番効果が高いとされています。
皮下組織の神経に作用させるのが経絡治療
西洋医学的にも皮膚から1ミリ~5ミリ程度の深さには真皮などの皮下組織が存在しています。
皮下組織には様々な神経が豊富に存在しており、それらの神経に刺激を加えることで自律神経に作用し、様々な効果が得られます。その為、経絡治療の鍼の深さは非常に理にかなっており、西洋医学的にも効果の高い治療法と言えます。
経絡治療と中医学の違い

同じ東洋医学には中医学という治療法、学問が存在します。経絡治療と中医学は全くの別物で、治療法が異なります。先ほど説明した証を立てた後に、その証に効くツボを少ない数選びます。1つや2つの場合もありますので、「この証にはこのツボ」としっかりと決まっている治療です。他にも漢方を同時に処方する事で体質を改善していきます。
経絡治療よりも体系化されており東洋医学と西洋医学の間が中医学という治療のイメージです。それとは対照的に体全体の経絡の滞りを細かく解消していくのが経絡治療になります。
経絡治療の批判・デメリット
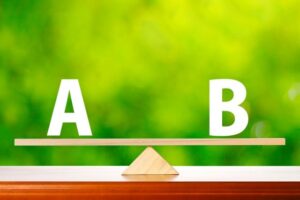
それほど効果の高い治療法でも批判されたりデメリットが存在することも忘れてはいけません。
脈診は術者の主観による体の評価なので、診る人によって患者の身体の評価が変わる可能性があるという事です。言語化し共有する事が困難な為、技術の習得には時間がかかり、技術を教えるのにも時間がかかるという事です。又、患者への説明も東洋医学の言語を用いり過ぎると「何を言っているかわからない」という感想を持たれやすい為、東洋医学の概念を上手に分かりやすく現代の言葉に変換して伝える必要があります。
デメリット:技術の習得に時間がかかる、人に教えるのが大変、治療の説明がしにくい
脈診経絡治療協会で知識と技術を習得しています
現在のパナソニックを作り上げた松下幸之助の専属の鍼灸師であった脈診経絡治療の第一人者、黒田先生の外弟子である上原先生が主催している脈診経絡治療協会にて知識と技術を学び臨床経験を積んでいます。実践で経絡治療を学び現在も臨床経験を積み重ねております。
当院の脈診流経絡治療で改善できる症状

病院の検査で異常が見られない原因不明の症状はほとんど対応する事ができます。
病気を治すのではなく、体質を改善する事で結果的に症状や病気が良くなるというのが経絡治療ですので、病名や症状にあまり囚われません。
西洋医学では治療法が無く、対処療法でしかない症状や病気でも、東洋医学なら改善する事ができます。中でも自律神経が関連する不調を得意としており、様々な症状に対応できます。
脈診流経絡治療で対応できる症状
- 自律神経失調症、不安障害(不安症)、異痛症(アロディニア)、睡眠障害(不眠症)、胸の不快感、動悸、息苦しさ(胸苦しさ)、ふわふわめまい、持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)、機能性ディスペプシア、逆流性食道炎、過敏性腸症候群、パニック障害(パニック症)、ヒステリー球(咽喉頭異常感症)、コロナ後遺症、頭鳴り、耳鳴り、口腔異常感症(口腔セネストパチー)、嗅覚障害、味覚障害、ブレインフォグ(脳疲労)、起立性調節障害、疲労感・倦怠感、生理痛、更年期障害、便秘、下痢、慢性疲労症候群、上半身のほてり、線維筋痛症など
脈診流経絡治療はどれくらいで治療効果が出るのか?

個人差はありますが、当院での鍼灸治療によって症状が改善するおおよその治療回数は8回前後です。
8回前後の施術を受けると調子が良い状態で安定してくることが多いです。
ですが、生活環境や生活習慣、心理的なストレスなどが関係する為、それらに影響され症状の波が出現しますので、人によって差はあります。
それらを加味した上で大体の人が8回前後の施術を受けると効果を実感してきます。
鍼灸治療の推奨ペース
症状が辛い場合、治療の初期段階では週1~2回のペースで治療し、症状が安定してきたら週1~2週に1回のペースで治療の間隔を空けていきます。
毎日受ければその分早く治るのかというとそうではありません。体質の変化によって体の機能が低下している状態ですので、症状が出ない元の体質に戻していくには一定の時間が必要になります。当院の治療の回数を加味すると2~3か月程の治療期間で症状が安定してくる方が多いです。(もちろん個人差はあります)
脈診流経絡治療を行っている鍼灸院は少ない

鍼灸治療には筋肉を狙って治療するような西洋医学的な治療をする鍼灸と経絡治療のような東洋医学的な治療をする鍼灸の大きく分けて2つの種類が存在します。ですが、年々東洋医学の治療ができる鍼灸師が減少してきており、現在は鍼灸院全体の1~2割程度しかないと言われております。その為、筋肉のコリや痛みに対応できる鍼灸院はあっても、自律神経や内臓の不調に対する治療ができる鍼灸院は少なくなっています。当院は数少ない東洋医学の治療を行っている鍼灸院です。
脈診流経絡治療を東京の町田で行っている

当院は東京の町田駅徒歩4分の場所で施術をしています。自律神経の不調に特化した東洋医学の経絡治療と痛みやシビレに特化したトリガーポイント鍼療法で様々な不調を改善に導いています。
横浜、小田原方面、八王子、東京、世田谷方面にお住いの方も多くご来院頂いております。
症状でお困りの方は下記のLINEからぜひ一度お問い合わせください。